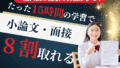朝の通学電車でスマホを開いた瞬間、数学の解説動画、教材レビュー、SNSの意見が一気に流れ込む。
先生の言い方と真逆の主張に挟まれ、頭が止まることはありませんか?
気づけば、タブをいくつも開いたまま、どれから手をつければいいのか分からなくなる──。
今の受験生が抱える「迷い」は、怠け心ではなく“情報の構造”に原因があります。
この記事では、認知心理学と学習科学の視点から、情報過多に負けない整理法と選択の設計術を紹介します。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
なぜ「多いほど安心」ではなく「多いほど動けない」のか
人間の脳には“ワーキングメモリ”という、情報を一時的に処理する装置があります。
この容量は限られており、無関係な刺激が増えるほど、肝心な理解や推論のリソースが奪われてしまいます。
この現象は「認知負荷」と呼ばれ、余計な装飾や比較情報が増えるほど、学習効率は下がるのです。
さらに、別タブや通知に注意が移った直後には“残り香”が残ります。
その結果、目の前の問題に戻っても集中が浅くなり、思考の流れが細く感じられることがあります。
つまり、混乱の原因は「時間の不足」ではなく、「注意の散り方」にもあるのです。
「分かったつもり」の罠に気をつけよう
動画や記事を見た直後、「理解した気がする」のは脳の錯覚です。
いざ白紙に書こうとすると、要点が抜け落ちている──これは“分かったつもり効果”と呼ばれる現象。
広く浅く情報を浴びたときに特に起こりやすく、ネット上の“信号と雑音”が混在する環境では避けづらいものです。
加えて、選択肢が多いほど意思決定は遅くなります。
問題集を並べて眺めるだけで一日が終わるのは、比較の基準が揃っていないから。
逆に、目的が明確で基準が決まっているときには、選択肢の多さがむしろ満足度を高めるという研究もあります。
情報過多に負けない「賢い絞り方」
最初のステップは、「入れる前に削る」。
つまり、情報を集める前に、信用基準を決めることです。
1️⃣ 一次資料を最上位に置く
大学が配布する出題範囲、公式シラバス、過去問と公表解説を軸に据えます。
次に専門書・学会資料などの二次資料を参考にし、SNSやブログの情報は“仮説扱い”で保留。
2️⃣ 二段フィルタで選別する
- 第一段:十数秒の「匂い取り」。発信主体・日付・根拠の有無を確認。
- 第二段:数分の「軽読」。主張が論理的か、自分の目標に関係するかを判断。
3️⃣ “良い十分”の基準を決める
最良を求め続けるほど探索は長引きます。
「合格に十分」というラインを明確にすることが、心理的安定を保つ鍵です。
頭を整える「見える化」とノート設計
情報をコンセプトマップで整理し、用語・因果関係・法則を線で結びます。
また、ノート作りには“コヒーレンスの原理”を応用し、要点と根拠だけを簡潔に書く。
余計な装飾を減らすだけで、理解の滑り落ちが減ります。
教材構成にも工夫を。
解法の手順を徐々に減らす「フェイディング」方式で段階的に自立。
さらに「先行オーガナイザ」(今日のゴール・前提・使い道)を冒頭に書くことで、情報が地図上に整理されます。
「探索→選定→統合→実践」の4ステップ設計
迷いを減らすには、情報処理の流れを固定化しておくことが効果的です。
【探索】
一次資料+過去問など「情報パッチ」を限定。
終了条件を「一次資料と矛盾がない」と明記。
【選定】
採用は常に3件まで。新情報を入れるときは必ず何かを外す「入替ルール」。
【統合】
採用した情報は自分の言葉で要約し、根拠(資料名・日付)を添える。
ノートの版を重ねて残し、判断の変遷を見える化します。
【実践】
例題→類題→初見の順に並べ、最後に「判断ログ」を一行残す。
「この解法を選んだ理由=見通しが良い」といった言語化が、次の探索の指針になります。
衝突する情報への対処と注意の守り方
情報が矛盾したら、まず一次資料を優先。
同格なら、当面の学習ゴールに直結する方を「暫定採用」し、週末に見直します。
こうして“保留の置き場”を先に作るだけで、迷いは減ります。
注意を守るには、机上からスマホを視界外へ。
学習用デバイスと娯楽用端末を分け、「休憩時にまとめて確認」する“まとめ見”方式を導入すると良いでしょう。
家庭と塾での活用例
家庭では、評価よりも工程設計の会話を。
「今日は何を入れて何を保留にする?」といった対話を夕食前に短く行い、子ども自身に「採用理由」を言語化してもらうことで、判断力が育ちます。
塾では、授業の冒頭に「採用宣言」を書かせ、宿題に「採用理由欄」を設けます。
週次で“保留棚おろし”を行うだけで、情報迷子がぐっと減ります。
最後に ― 迷いを減らすための習慣を
情報の多さに押し流されるのは、性格ではなく構造の問題です。
一次資料を軸に、二段フィルタ・十分基準・保留ルールを設ければ、情報の海は整理された“航路”に変わります。
今日の学習を始める前に、「何を入れて、何を捨てるか」を短く宣言してみましょう。
その一言が、迷いを断ち切る最初の舵取りになります。
学力とは、迷いを減らして動いた時間の総和。
そして、家族や先生と“工程語”で対話を重ねることで、情報に飲み込まれない日常が続きます。