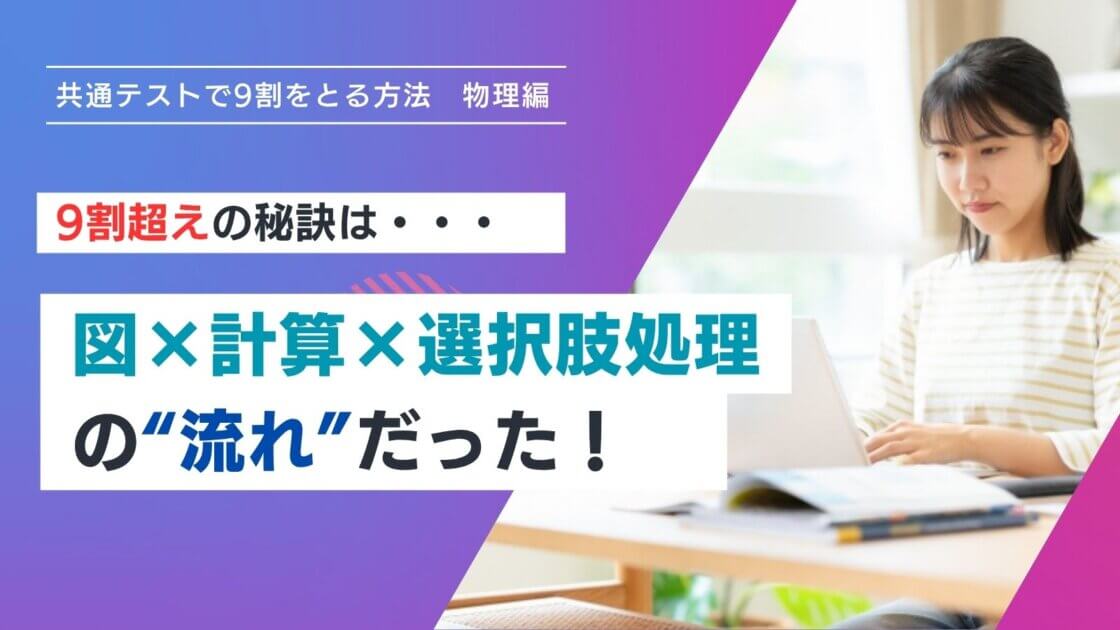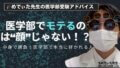物理はセンスじゃない。論理で勝つ
「公式を覚えて当てはめるだけじゃ、点が取れない…」
「全部の選択肢が正しそうで、迷ってしまう」
「計算が合ってるのに、正解が見当たらない」
共通テストの物理でこうした悩みを抱えているなら、それはむしろ“物理の点数を上げる素地”がある証拠です。
今の物理は、「公式の丸暗記」だけで得点できる時代ではありません。問われているのは、実験設定の読解力、現象の因果関係を追う論理的な力、そして何より、「なぜそうなるのか」を根本から理解する力です。
この記事では、物理が苦手な人も得意な人も、共通テストで安定して9割を取るための具体的な方法を紹介します。出題傾向の分析から、公式の活用法、典型問題の処理、実験問題の解法、本番での時間配分まで。
今すぐ始めよう。物理9割への“思考の流れ”が、ここから始まります。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
第1章:共通テスト物理の出題傾向と攻略の全体方針
【全体傾向】
- 図やグラフ、実験設定を含む問題が中心。
- 選択式の設問が多く、計算結果そのものより“論理的判断”を求められる。
- 問題文が長文化し、読解力との融合が進んでいる。
- 時間的余裕が少なく、処理スピードも重要。
【出題構成(例年)】
- 力学:小問集合、運動方程式、力のつり合い、運動エネルギーなど
- 波動:縦波・横波、音波、干渉・ドップラー効果など
- 電磁気:オームの法則、コンデンサー、電磁誘導、回路など
- 熱・原子:理想気体、放射線、光電効果など
- 実験問題:複数の項目を組み合わせた探究的な出題
【攻略の基本方針】
① 公式の意味を理解して使う
公式は暗記するものではなく、「どんな現象を、どんな条件で表しているか」を理解する道具です。たとえば運動方程式は「物体に力が加わるとどう変化するか」を表しています。
② 図を描く、図から考える
文章を読んで終わらせるのではなく、「図にする → 向き・大きさ・関係を見る」を習慣に。視覚化が理解への第一歩です。
③ 計算を省略しない
見た目で「合ってそう」に騙されず、「式立て → 代入 → 単位確認」を徹底しましょう。
④ 時間配分を意識した練習を重ねる
すべてに時間がかかる物理こそ、通し演習で「1題あたりにかけられる時間」を体で覚える必要があります。
第2章:基礎力の鍛え方と日常学習で意識すべきこと
【1. 公式は“使える形”で覚える】
- どのような条件で使えるか(例:加速度一定)
- 何と何の関係を表しているか
- グラフ化するとどんな形か
→ これらを言葉で説明できるようにしておきましょう。
【2. 「なぜそうなるか」を言語化する癖をつける】
- 解説を読んだら、自分の言葉で説明
- 友人や自分に向けて、図を描きながら口頭で解説
→ アウトプットこそが最強の学習法です。
【3. 教科書レベルの問題は“完答”を目指す】
- 『セミナー物理』や『リードα』を3周
- 解けなかった問題はチェックを入れ、再挑戦
- 解答だけで終わらず「なぜこの流れか」を再確認
【4. 図・グラフの扱いに慣れておく】
- 力のつり合いの図を描けるか
- v−tグラフやx−tグラフが読めるか
- 電流や電圧を視覚でイメージできるか
→ 見るだけでなく「描く練習」を!
【5. 1問に時間をかけすぎない感覚を養う】
- 「15分以内で結論を出す」意識
- 解けなかったら解答を見る→翌日解き直す
→ “わかった気”から“できる実力”へ
第3章:大問別攻略法と設問処理のテクニック
【1. 力学:基本を極める最重要分野】
- 出題率が最も高く、設問数も多い
- v–tグラフやx–tグラフの読み取りも頻出
攻略法:図を描く・単位の確認・運動の種類を即判断
【2. 波動:式より“意味理解”で差がつく】
- 音波・ドップラー効果・干渉などが出題対象
攻略法:用語の明確化・動くものの把握・波の図の徹底
【3. 電磁気:公式暗記型から“仕組み理解型”へ】
- 回路図や磁場問題、コンデンサーなど典型問題が多い
攻略法:パターン問題の演習・図を描き直す習慣・単位検算
【4. 熱・原子:確実に拾う“得点調整パート”】
- 難問少なめ。基本知識で得点可
攻略法:軸・面積=仕事を意識したグラフ読み・正確な計算
【5. 設問処理テクニック:選択肢で“迷わない力”】
- 条件の線引き・選択肢の検証・根拠の言語化
- 正誤理由を説明できることが最終ゴール
第4章:直前期の仕上げ方と本番戦略
【1か月前:弱点補強と過去問演習】
- 正答率の低い大問を重点復習
- 時間を測って演習
- ミスノートで繰り返し確認
【1〜2週間前:出題パターンの最終整理】
- 頻出設定を短時間で確認
- グラフ・図問題の見直し
- 根拠の言語化を意識した復習
【前日:メンタルの安定を最優先】
- 夜更かし厳禁。リラックス重視
- 当日の動きをイメージトレーニング
- 「やるべきことはやった」と自分を信じる
【当日:冷静さと柔軟性を保つ】
- 時間配分をざっくり把握
- 難問は後回し
- 終了5分前は見直しタイムに
【持ち物・準備リスト】
- 時計、筆記用具、受験票、ICカード
- 軽食(チョコ・ナッツ・ゼリーなど)
- 苦手まとめノート(直前復習用)
まとめ:論理的に積み重ねれば、物理で9割は誰にでも届く
共通テストの物理で9割を狙うということは、難関大合格への大きなアドバンテージになるだけでなく、自分の“論理的な思考力”を証明することにもつながります。
そのために必要な4つの柱は──
- 出題傾向を理解して、学習を効率化する
- 公式を“意味のある道具”として使う
- 図・グラフ・選択肢に強くなるための訓練
- 「できることを確実にする」マインドをもつ
物理が苦手だと思っている人も、正しいやり方で学べば必ず得点源にできます。
好きで得意な人も、抜けがちな計算ミスや読み落としを潰すことで安定した得点が可能になります。
大切なのは、「難しいから」ではなく「理解できるまで粘ったから」点が取れたという経験を積むこと。
共通テスト本番、焦らず、慌てず、自分の思考の流れを信じて臨んでください。
君なら、必ずやれる。