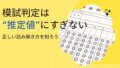模試の後、自己採点をして「どこから直せばいいの?」と手が止まる──。
そんな経験をしたことはありませんか?
点数だけを眺めても、次の一手は見えてきませんし、解説を読むだけでは学びが浅くなりがちです。
だからこそ、模試直後の数日を「記憶を強くする復習」「原因を分解する分析」「次の模試に効く計画」の三段階に分けて進めることが大切です。
本稿では、研究に裏付けられた効果的な方法を、高校生と保護者にも使いやすい手順で紹介します。
万能な方法はありませんが、“自分に合う型”を少しずつ整える姿勢こそが、継続と成果につながります。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
試験直後の行動が9割を決める
まずは“答案が返る前”の処理から始めましょう。教室を出た直後から当日中に、思い出せる範囲で設問と自分の思考をメモします。
この「直後再生」は、確認の前に思い出す行為そのものが学習になるからです。いきなり解説に飛びつくよりも、先に自力で再現した方が定着が深まります。
次に「三色マーク」を使って答案を整理します。
- ○=確信ありで正解
- △=迷いながら正解
- ×=不正解
さらに△と×を「知識欠落」「手順迷子」「読み違い」「時間切れ」に分類し、原因を特定します。分類の目的は、改善の矢印を一本に絞ることです。
また、各大問にかかった時間や見直し時間の有無を簡単にメモしておきましょう。細かすぎる記録は続かないので、必要最小限がポイントです。
ここまで終えたら初回の復習に入ります。最初に行うのは「自己採点+根拠の一文追記」。
正解・不正解の判定だけでなく、選択や解法を支えた“根拠”を一文で書き残します。
根拠を書けない正解は“偶然の的中”であり、次の演習で再確認すべき項目です。
誤答を“素材”に変える分解術
誤答の扱いは、“丸付けで終わらせない”ことが出発点です。
まず「ハイパーコレクションノート」を作りましょう。
自信満々で外した問題だけを集め、なぜ間違えたのか・正答はどう導くのかを短くまとめます。
驚きを伴う訂正は強い記憶として残りやすく、次の得点源に変わります。
続いて「根拠の再構成」を行い、不正解を選んだ理由を文章化します。どの段階で誤りが混入したかを特定し、計算・定義・読み取りなどの“ズレの地点”を丸で囲みます。
ここで役立つのが「セルフ・エクスプレイネーション(自説明)」です。解説の各行に対し、「なぜそうなる?」を声に出して答えることで、理解の穴を埋めていきます。
さらに「例題への逆流」もおすすめです。難問を繰り返すより、構造が近い例題に戻って骨組みを掴み直しましょう。
最後に、間違えた論点だけを集めて自作の「再出題テスト」を作ります。
答えを覚えるのではなく、“正しい手順を再生する”ことが目的です。
この再出題は一度きりでは終わりません。「間隔をあけた再現」を二回以上入れ、忘れかけた記憶を呼び戻します。
また、異なる単元を混ぜる「インターリービング」を取り入れることで、見分ける力が鍛えられます。
次の模試へつなげる計画
誤答を素材に変えたら、次の模試へつなげましょう。
まず「設問マップ」を作り、模試の各大問を「知識・手続き・読解・時間管理」の四軸で自己評価します。
印が重なった箇所は基礎に戻り、散らばった場合は学習順を見直します。
次に「時間配分の再設計」を行い、制限時間の九割で解き、最後の一割を見直しに使うルールを設定します。
英語は設問先読み、数学は易問先行、国語は主語・述語の構造確認──科目ごとの“入口の型”を明確にしておくと安心です。
また、「再出題→間隔再現→類題化」を翌週の学習計画に組み込み、短く繰り返すリズムを作りましょう。
模試返却時には「エグザム・ラッパー(振り返りシート)」を使って配点・時間・改善点を可視化します。
さらに「誤答の似顔絵カタログ」を作成し、自分が引っかかりやすいパターンを整理。模試前に3分だけ見直すだけでも効果的です。
演習では、問題の順番・配点・制限時間を本番同様に設定し、“採点者の視点”で答案を読み直しましょう。
科目別の復習ポイント
- 数学:誤りの原因を「定義理解」「式変形の精度」「方針選定」に分け、等号の意味を確認。
- 英語:根拠の英文を必ず引用し、設問先読みの有無を固定化。
- 国語:傍線部の「何について・どう述べているか」を主語・述語で復元。
- 理科:変数の統制を赤で囲み、代替案を一行添える。
- 地歴公民:「AだからB」「Bの結果としてA」を時間軸で整理。
無理なく続けるための工夫
完璧を目指すより、“最小完了ライン”を設定しましょう。
「直後再現は3問」「根拠の一文は1問」「再出題はA4半分」など、達成可能な範囲に留めることで継続しやすくなります。
保護者は「点数」より「手順」に焦点を当てた声かけを。
教師は「部分点の基準例」や「ルーブリック評価」を共有することで、振り返りの質が上がります。
模試フォルダを「学年→月→科目」の三階層で整理し、関連資料をひとまとめにすると復習効率が上がります。
習慣に落とし込む週次ループ
復習を続けるにはリズムを固定化します。
例:
月曜=答案整理/火曜=根拠再構成/水曜=再出題/木曜=類題化/金曜=時間配分通し/土曜=概念図/日曜=軽い復習と休養。
この一週間ループを固定するだけで、模試期の忙しさにも対応できます。
最後に──「今日の3つ」で次へ進もう
模試の後にすべきことは、丸付け以上の“設計”です。
直後は自力再現で記憶を強くし、三色マークとラベルで原因を分解。誤答は「根拠の再構成→自説明→例題への逆流→再出題→間隔再現→類題化」で扱います。
焦ったときは点数ではなく手順に戻ること。
今日の一歩はこの3つで十分です。
①直後再現 ②誤答の根拠一文 ③翌週の再出題予約。
小さな歯車を回せば、次の一歩が軽くなるはずです!