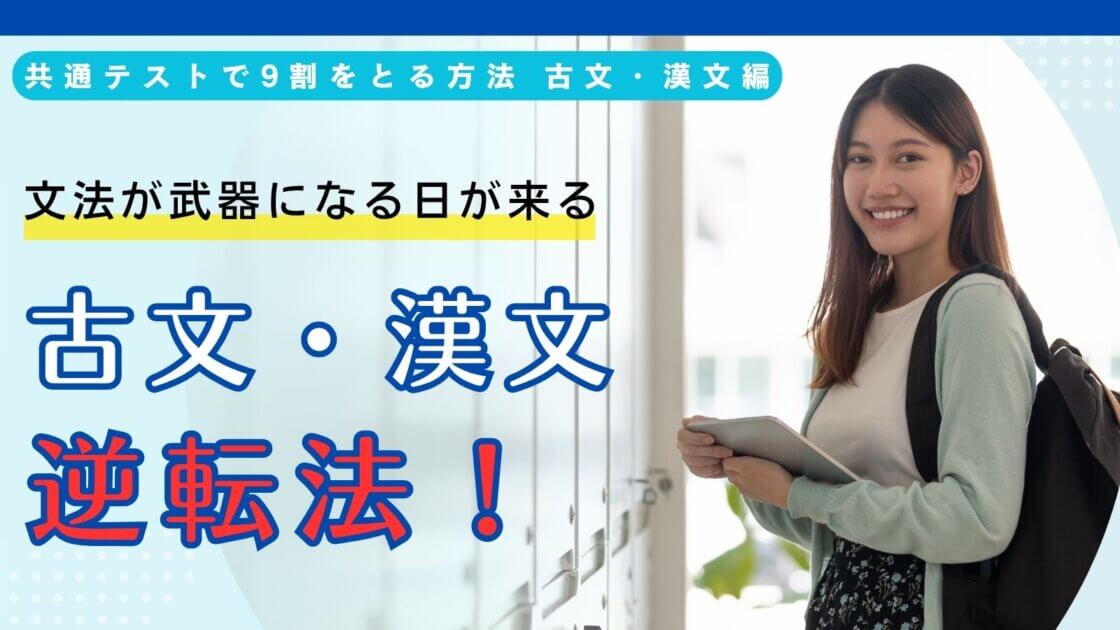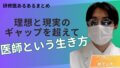古文や漢文は、「文法や句形を覚えるのが面倒」「読みにくいし面白くない」と感じて、つい後回しにしてしまう人も多いかもしれません。でも実は、この2科目こそ“型”を覚えておけば安定して得点できる“再現性の塊”のような存在なんです。
筆者自身の経験からも断言しますが、古文・漢文は「努力が得点に直結しやすい」超コスパ科目。文法、語彙、句法、そして敬語や漢字の意味など、しっかりと整理・暗記して、演習で定着させていけば、共通テストで9割は十分に狙えます。
この記事では、古文・漢文に共通する基本戦略から、得点につながる具体的な勉強法、直前期のチェックリストまでをぎっしりまとめました。苦手を武器に変えるヒントがきっと見つかるはずです。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
第1章:共通テスト古文の出題傾向と9割を取る読解戦略
古文は「文法」「語彙」「背景知識」の3つが揃えば、かなり高精度で読めるようになります。逆にどれか1つでも欠けると、いきなり読解が厳しくなる科目でもあります。
【共通テスト古文の特徴】
- 出典は『源氏物語』『伊勢物語』『徒然草』など、平安~江戸時代の作品が中心。
- 設問は内容理解(心情や状況)、文法問題(助動詞・敬語)、語句解釈、現代語訳が主。
- 文章量は多めでも設問形式はスタンダード。典型パターンを押さえれば得点しやすいです。
【文法を固める=読解の出発点】
- 助動詞(けり、つ、ぬ、たり、り、らむ、べしなど)の意味・活用・接続を一覧で暗記。
- 敬語の尊敬・謙譲・丁寧の使い分けは「誰に敬意を払っているか」を判断材料に。
- 係り結び(ぞ・なむ・や・か→連体形、こそ→已然形)は必ず文構造で覚えましょう。
【語彙・和歌・文学常識のインプット】
- 古語300語はしっかり覚える(いみじ、おぼゆ、あはれ、などは頻出)。
- 和歌の序詞・掛詞・枕詞の知識、さらに和歌が出る文脈も意識。
- 宮廷文化や恋愛事情、出家・身分制度など背景知識があると一気に読みやすくなります。
【読解の型を身につけよう】
- 登場人物の相関図を作りながら読もう。
- 主語が省略されがちなので、敬語から主語を補う技術が大切。
- 「誰が」「誰に」「何をしたのか」を段落ごとにまとめて整理!
【問題演習で戦略を磨く】
- 共通テスト形式の問題で、よく問われるポイントを分析。
- 間違えた問題は「なぜ読めなかったか」を記録して、二度と同じミスを繰り返さないようにします。
第2章:文法・敬語問題の得点力を鍛える解法パターン
文法・敬語問題は得点源。型を覚えればほぼ確実に得点できるので、ここを落とすのは本当にもったいないです。
【助動詞の識別パターン】
- 推量系(らむ、けむ、む、べし):文末・主語位置で判断。
- 過去・完了系(けり、き、つ、ぬ、たり、り):用法と意味をセットで暗記。
- 可能・受身・尊敬(る、らる):動詞の種類(自動詞か他動詞か)と主語で判断。
【敬語のポイント整理】
- 尊敬語:おはす、給ふ=主語に敬意。
- 謙譲語:参る、奉る=相手に敬意。
- 丁寧語:侍り、候ふ=会話相手に敬意。
→ 文の敬語が出てきたら、誰の動作で、誰に向けた敬意かをセットで考える癖を。
【係り結びの見抜き方】
- 係助詞と結びの形の組み合わせをミスらないように。
- 「こそ」が出たら已然形を探せ!
【問題処理の手順】
- 該当箇所を確認
- 意味・活用・接続を即答できるかチェック
- 主語や敬語の方向を補って判断
- 不明な知識は深追いせず、選択肢から除外
第3章:漢文の出題傾向と9割を取る句法・語彙戦略
漢文は「パターンと語彙」の把握でスコアが一気に安定します。句法と返り点が肝!
【出題傾向】
- 出題は論説(儒教・処世訓など)が中心。
- 設問は句法・語彙の意味・内容理解・主張把握。
- 書き下し文と選択肢がセットなので、現代語訳力が求められる。
【最頻出句法を押さえよう】
- 再読文字:未・将・当・応・能・可・須・猶・由
- 否定形:不・非・無・勿・莫 など
- 使役・受身:使・令・遣・被・見・所
- 疑問・反語:豈・安・何・孰・焉 など
例文ごと丸暗記して、構造と意味を完全に一致させるのがカギ。
【句形は構造で覚える】
- A使BC=AはBにCさせる(使役)
- A為B所C=AはBにCされる(受身)
- A豈B乎=AがどうしてBだろうか(反語)
形式と語順、意味をセットで覚えよう。
【語彙力も不可欠】
- 「義」「仁」などは文脈で意味が変わる。複数の意味を持つ語は要注意。
- 同音異義語、似た意味の語はセットで比較整理を。
【返り点の処理と書き下し】
- レ点、一二点、上下点の基本は毎回確認。
- 書き下しは音読・意味付け・現代語訳の3ステップで行う。
- 主語・述語・目的語の位置関係を即座に捉える練習が肝心。
第4章:設問処理と時間配分の戦略
解ける問題を確実に取り切るには、「読む前の準備」と「時間配分」が超重要。
【設問を先に読む】
- 本文を読む前に設問(特に文法・現代語訳)を確認。
- どこを読むべきか、何が問われているかの“目的”を持って本文に入る。
【本文の読み方を工夫】
- 最初の1文・段落の末文は重点チェック。
- 古文:敬語と主語に注意。
- 漢文:返り点と句法をその都度チェック。
【時間配分の基本】
- 古文:10〜12分、漢文:8〜10分
- 各設問:1分以内。悩んだら仮決定して保留。
- 後回し戦略で“解き残しゼロ”を目指す。
【選択肢処理のコツ】
- 本文の根拠を先に探す→選択肢を判断。
- 明らかにずれた評価・語句を含む選択肢は真っ先に除外。
【ケアレスミスを防ぐ】
- 「正しいもの」「不適当なもの」など設問文を赤で囲んでおく。
- 解答後の10秒見直しで設問の読み違いを潰す。
最終章:復習法・直前対策・本番への心構え
努力の方向性が合っていれば、古文・漢文は「点が取れる」自信に変わります。
【復習の基本】
- 問題を解いたら「なぜ正誤を判断したか」を必ず言語化。
- ミスの原因を分類し、復習ノートで3日・1週・1ヶ月後に再確認。
【暗記の定着法】
- スキマ時間は単語帳・文法カードを音読しながら確認。
- 和歌や再読文字は場面・文脈と一緒に覚えると忘れにくい。
【直前期の勉強法】
- 過去問のやり直しが最強。ミス潰しを優先。
- 新しい問題よりも「確実に取れる問題を落とさない」意識で。
【本番でのメンタル】
- 古文・漢文は“知識武装すれば勝てる科目”。
- 見たことある構文、覚えた句形が出たら、自信を持って突き進もう。
- ミス1問にこだわらず、解ける2問を取りに行く意識で。
まとめ:古文・漢文で得点を取りきるには
古文・漢文は、「型を覚える → 問題で確認 → 復習で定着」のサイクルを回せば、必ず伸びる科目です。
暗記と演習の“質”を高めることで、苦手意識はいつの間にか「得点源」に変わっていきます。
あなたも今日から、自分なりの“得点ルート”を磨き始めてください。