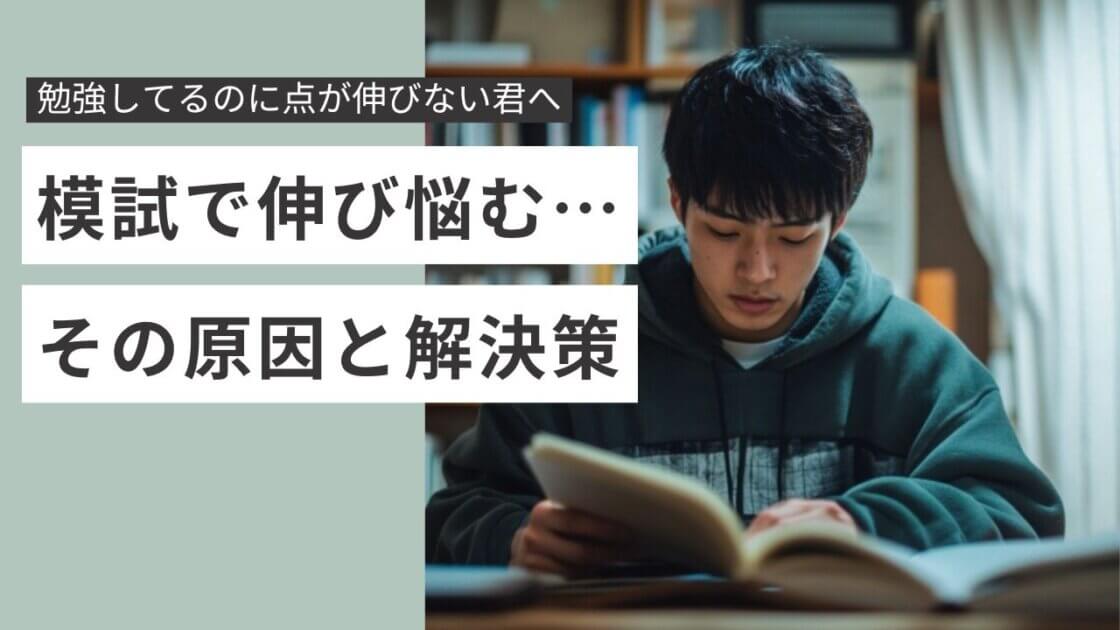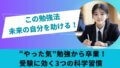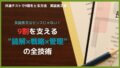みなさん。模試を受けて「判定がずっとCのまま」「自己ベストを超えられない」「ケアレスミスが減らない」と悩む声を、私もよく耳にします。努力を重ねているのに点数が動かないと、不安にもなりますよね。
ですが、どうか誤解しないでください。その原因は“やる気不足”ではありません。伸び悩みの正体は、学習の設計や復習の質、さらにはテスト当日の運用方法が噛み合っていないことにあります。
今日は、認知科学の研究と教育現場の知見をもとに、「なぜ点が伸びないのか、どうすれば改善できるのか」を、一緒に確認していきましょう。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
伸び悩みの正体は「学び方の仕組み」にある
- 暗記や読み直しでは記憶が長く残らない
- 思い出す練習(想起)が記憶を強化する
- 模試で問われ方が変わっても対応できる基礎体力をつける
「テスト効果(retrieval practice)」と呼ばれる学習法は、再読より効果が高いとメタ分析でも示されています。
分散学習の力──直前ブーストでは限界がある
- 一気に詰め込むより、間隔をあけて繰り返す方が効果的
- 「翌日→3日後→1週間後→1か月後」のサイクルが王道
- 夏休みの総復習も、刻んで再テストするほうが効率的
この「間隔効果」は教育現場でも再現され、長期保持に最強クラスの知見とされています。
混合練習(インターリーブ)の効果
- 同じ種類の問題を固めると“できる気”になるが本番で崩れる
- 単元を混ぜることで解法選択の判断力を養える
- 練習中は手応えが落ちるが、本番の得点は上がる
これは「望ましい困難」の典型例です。
戦略の骨格──5つの柱
- テストで学ぶ
短いテスト×遅延フィードバックを軸に学習を再設計。 - 分散×想起×混合
追いテストを日程に組み込み、単元を混ぜながら連続成功を積む。 - 原因の可視化
誤答をタグ化し、同パターンを3題解き直すことで再学習に変換。 - 時間運用の仕組み化
If–Thenプランで行動を自動化し、迷いを減らす。 - メンタルの調整
表出書記や価値肯定で不安を軽減し、当日のパフォーマンスを守る。
実践方法──模試をループで回す
① 前週までの準備(7〜2日前)
- 毎日20〜30分の混合ミニテスト
- 採点は翌日以降にして遅延フィードバックを作る
- 再学習の台帳に「+1・+3・+7日」の追いテストを予約
- If–Thenプランを3本だけ設定
② 前日〜当日朝
- 新規学習は控え、弱点タグ別の練習を回収
- 当日朝は短時間の想起テスト+表出書記で心を整える
③ 模試の最中(運用)
- 大問で粘らず3分で切り替えるルール
- 見直しは「配点→計算量→根拠の明確さ」の順に優先
- 解答変更は“誤→正”の方が多いというデータを信じて実行
④ 48時間以内の復習
- 誤答を5〜8個のタグに分ける
- タグ別に同パターンを3題解き直す
- 「自信度」と実際の正誤を比較し、過信領域を補正
⑤ 次の模試まで(2〜4週間)
- 週1回は“入試リハ”を制限時間つきで実施
- 数学・理科は混合練習、英語・国語は設問先読みの型を固定
- 平日はミニテスト、休日は積み残し回収に充てる
よくある詰まりと解決法
- 復習時間がない → 学習そのものをテスト形式にする
- 覚えが薄い → +1・+3・+7の追いテストを固定化
- 練習ではできるのに本番で落とす → 混合×分散練習が不足
- 見直しで迷う → 解答変更はエビデンス的に“あり”
今日から使えるテンプレ
- 英語:単語20個の想起テストを毎晩→+1・+3・+7日で追試
- 数学:例題→自力→翌日テスト→土曜は混合セット
- 国語:設問先読み→本文マーキングを習慣化し、タグ別回収
- 理社:図表や年表の穴埋め想起→短回しサイクル
- メンタル:模試当日朝に10分の表出書記
保護者の方へ
声かけは「点数」ではなく「行動」に焦点を当ててください。
「タグ分け終わった?」「+1・+3・+7の追試は予定に入ってる?」といった確認が、子どもの自己効力感を支えます。
まとめ
模試の点が伸び悩むとき、必要なのは量ではなく「仕組み」の改善です。
- 分散×想起×混合
- 遅延フィードバック
- 誤答タグによる可視化
- If–Thenでの時間運用
- 本番前の表出書記
これらを組み合わせれば、“望ましい困難”を超えて本番で点数に結びつく学習ループが回り始めます。
努力を無駄にせず、次の模試を確かな一歩にしていきましょう。