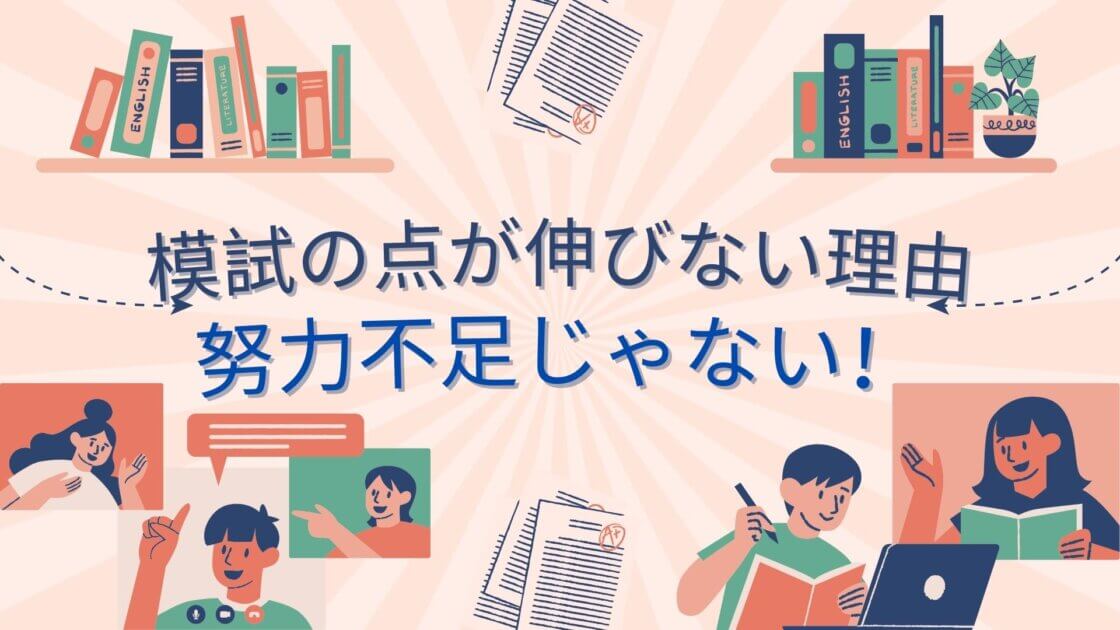「判定がずっとCのまま」「自己ベストを更新できない」「ケアレスミスが減らない」──。
こうした悩みは、模試を受け続ける受験生にとって“あるある”ではないでしょうか。SNSを見ても、同じ声が数多く上がっています。
ただし、点が伸びない理由は「やる気不足」ではありません。多くの場合は、学習設計・復習法・当日の運用がうまく噛み合っていないだけなのです。
実際、認知心理学や教育学の研究では「思い出す練習(テスト形式の想起)」や「分散学習」「混合練習」といった手法が、確実に学習成果を押し上げることが示されています。つまり、模試の点が伸びないときこそ、やり方を少し変えるだけでブレイクスルーが訪れるのです。
この記事では、最新の学習科学に基づきながら「模試で点が伸びない理由」と「実際に取り入れられる戦略」を、受験生も保護者もすぐに実践できる形でまとめました。

記事の監修者:五十嵐弓益(いがらし ゆみます)
【全国通信教育】最短合格オンラインのスカイ予備校 校長
■小論文指導歴27年
これまでに指導した生徒は4000人以上、独自のSKYメソッドを考案で8割取る答案の作り方を指導。
2020年4月から、完全オンラインの大学受験予備校となる。過去3年間で国公立大学合格125名。
高1から入会者は国公立大学合格率93%
高2から入会者は国公立大学合格率86%
高3の4月から入会者は国公立大学合格率73%。
スカイ予備校の指導方針は、「大人になっても役に立つ勉強法の習得」です。「自分の人生は自分で切り拓く」教育をします
伸び悩みの正体
「判定がずっとCのまま…」「自己ベストを超えられない…」「ケアレスミスが減らない…」
こんな悩み、あなたも感じたことはありませんか?
💬 「あれ?頑張ってるのに、なぜか点数が伸びない…」
安心してください。それは“やる気不足”が原因ではありません。多くの場合、学習の設計や復習の質、テスト当日の運用がうまくかみ合っていないことが原因です。
まず押さえたいのは「練習=得点力になる仕組み」です。暗記や読み直しだけでは長期記憶に残りにくいですが、“思い出す練習(テスト形式の想起)”は記憶を強化し、応用力にもつながります。
💬 「再読よりテストで学ぶ方がいいの?」
はい、その通りです。研究でも、テストで学び直す方が成績に直結することがわかっています。しかも、出題形式が変わっても応用できる力がつくので、模試で問われ方が違っても踏ん張れる基礎体力になります。
次に大事なのは時間のかけ方です。いっきに詰め込むより、間隔をあけて繰り返す(分散学習)が記憶の持続に効果的です。直前だけの追い込みでは伸びにくいのも、このためですね。
さらに、同じ種類の問題だけを固めると練習中はできた気になりますが、本番ではミスが増えます。そこで効果的なのがインターリーブ(単元混合)練習です。
💬 「え、練習で手応えがない方が良いってこと?」
その通り。練習中の手応えが落ちても、本番点は上がります。これが“望ましい困難”です。
では、どこから手をつけるのが効率的なのでしょうか?ここから戦略の骨格を固め、具体的な実践方法に落とし込みます。
戦略の骨格
1. 「テストで学ぶ」への転換
模試の点が伸びないと、つい参考書やノートの再読に走りがちですが、短時間のテスト×頻回フィードバックに置き換える方が得点に直結します。
💬 「フィードバックって、答え合わせのこと?」
そうです。ただし、遅延フィードバック(少し時間を置いて答え合わせ)を組み合わせると、さらに定着率が上がります。学力への影響も大きいと研究で示されています。
2. 「分散×想起×混合」の三点セット
週ごとのカレンダーにミニテストを配置し、1日後・3日後・7日後の追いテストを組み込みます。単元を混ぜることで解法選択の練習になり、類題を絞って“連続成功”を作ると自己効力感も保てます。
3. 「点が伸びない原因の可視化」
採点後48時間以内に、間違いを原因ごとにタグ付けします。読解なら〈設問の主語取り違え〉〈根拠行の見逃し〉、数学なら〈定義の想起失敗〉〈計算手順の逆〉などです。
💬 「なるほど、ただ反省するだけじゃダメなんですね」
はい。同じタグの問題を3題解き直すと、反省が次の学習設計につながります。
4. 「時間運用の仕組み化」
時間管理は学業成績やメンタル面とも関係があります。“いつ・どこで・何を”まで決めるIf-Thenプランを作り、自動化してしまいましょう。
例:
💬 「20:30になったら机に座って英語テストを始める!」
5. 「本番に向けたメンタルのチューニング」
テスト不安が強い人ほど、試験直前の“表出書記(worryを書き出す)”が有効です。10分ででき、コストも小さいのでテンプレートを使って淡々と回すのがおすすめです。
実践方法
模試→復習→次の模試までを一本のループとして設計します。
① 前週までの準備(7〜2日前)
- 混合ミニテストを1日1セット(20〜30分)
- 連続再学習の台帳を作る
- 学習のIf-Thenを3本設定
💬 「これなら迷わず始められそう!」
② 前日〜当日朝
- 新規学習は最小限。タグ別弱点パックを15〜20分で一周
- 当日朝は試験条件での想起1セット+表出書記10分
③ 模試中
- 時間の“前借り”をしない
- 見直し優先順位を決める
- 解答変更は損ではない
④ 48時間以内の復習
- 誤答をタグ分け、タグ別3題で再学習
- 自力想起→遅延答え合わせを徹底
- メタ認知のずれを補正
⑤ 次の模試まで(2〜4週間)
- 週1回“入試リハ”30〜60分
- 数学・理科はインターリーブ、英語・国語は設問先読み→根拠マーキング
- 平日はミニテスト×遅延フィードバック、休日は時間配分練習
よくある詰まりと解決
- 復習時間が取れない → 学習そのものをテスト化
- 覚えが薄い → +1・+3・+7の追いテスト
- 練習では正解するのに本番で落とす → 単元混合+選択練習
- 見直しで迷う → 根拠が補強できれば変更推奨
今日から使えるテンプレ
- 英語:毎晩20分、単語20個の想起テスト→翌日・3日後・7日後追試
- 数学:例題→自力→翌日テスト。土曜は混合セットで解法選択を鍛える
- 国語:設問先読み→本文マーキング固定、ミス要素をタグ化
- 理社:地図・年表・図表の穴埋め想起。1→3→7日の短回し
- メンタル:模試当日朝10分の表出書記
保護者の方へ
声かけは“行動に焦点”を。
💬 「何点だった?」よりも、「タグ分け済んだ?追試予定は?」
行動のトラッキングで自己効力感を支えます。スケジュールが崩れたら、If-Thenを一つ見直して再開ハードルを下げてあげてください。
まとめ
模試の点が伸びないときは、「分散×想起×混合」と“遅延フィードバック”を核に、成功ループを回すのが近道です。誤答タグで原因を可視化し、同パターン3題で連続成功を作ると自己効力感が戻ります。If-Thenで時間運用を自動化し、当日は表出書記で不安を減らす。練習中の手応えが薄くても、それは望ましい困難のサイン。本番の点で答え合わせすれば、次の模試が確かな一歩になります!
💬 「今日から少しずつ試してみよう!」